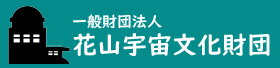はじめまして。元花山天文台長、花山宇宙文化財団理事長の柴田一成です。
みなさんは、京都市山科区にある花山天文台を訪れたことはあるでしょうか?
花山天文台は国内で2番目に古い大学天文台です。太陽コロナ(1940年代)、火星の気象学の開拓(1950年代)、アポロ計画のための月面地図づくりへの貢献(1960年代)などの太陽系天体の観測的研究で世界的な成果をあげてきました。
また、初代台長の山本一清博士は、日本初のアマチュア天文同好会を組織し、アマチュア天文家の育成活動を非常に熱心に推進したため、花山天文台はアマチュア天文学の聖地と呼ばれてきました。
花山天文台が保有する望遠鏡はどれも世界レベルの優れものです。
本館の「45cm屈折望遠鏡」は、屈折鏡としては国内三番目の大きさを誇り、かつて火星や月の観測で活躍しました。今は研究の第一線は退いたものの市民向け観望会では大人気です。
現役望遠鏡としては日本最古114歳の「ザートリウス製18cm屈折望遠鏡」は、Hαフィルターを搭載することで現在も常時太陽フレアやプロミネンスのモニター観測で大活躍。
日本第二の大きさの太陽分光望遠鏡がある「太陽館」では大学や高校の観測実習が行われ、太陽スペクトル観望は「本物の色が見られる体験」として、市民向け見学会で多くの人を魅了しています。
古いけれど、教育普及用には、きわめて貴重な価値のある望遠鏡群がある花山天文台ですが、この数十年にわたる国立大学の運営費の削減により、存続が困難になってきました。 2018年に京都大学の岡山天文台が完成し、既存の天文台の運営費が削られ、花山天文台は閉鎖の危機に瀕することになりました。
ある年、ロンドン郊外のグリニッジ天文台を訪問しました。多くの見学者でにぎわう有名観光地は、古い建物や装置、望遠鏡がきちんと保存され、丁寧な展示解説もあり、ときには観望会も開催。最新式のプラネタリウムに天文博物館、土産物ショップ、レストランまでありました。
これぞ花山天文台の目指すべき将来ではないか、と思いました。
グリニッジ天文台の面積はちょうど花山天文台と同じくらいです。花山天文台の空いている土地を使うと、プラネタリウムや科学館を十分作れます。
あるときミュージシャンの喜多郎さんが「花山天文台に野外音楽堂をつくりましょう。素晴らしい自然に囲まれているし、京都にあるので、世界中からミュージシャンが来ますよ」とおっしゃったアイディアがもとになり、将来構想がまとまりました。
喜多郎さんを筆頭とする多くの市民のみなさまの応援のおかげで、花山天文台を市民の力で残していこうという機運が高まり、2019年、香川県高松のクレーンの世界的企業タダノの社長(当時)・多田野宏一氏によって花山天文台を財政的に支援する花山宇宙文化財団が設立されました。元京大総長の尾池和夫先生が財団の初代理事長を務めてくださり、2021年6月からは私が二代目理事長を務めています。
次世代に向けて、より多くの人々、特に子どもたちに花山天文台を見学してもらいたいと考えています。近代日本の天文学を支えてきた学びの場を、時代に沿うようつくり替え、次世代に引き継いでいくことに私の残りの人生を賭けたいと思います。
みなさま、花山天文台、そして、花山文化宇宙財団を、ぜひご支援ください。
2025年4月1日
理事長・柴田一成プロフィール
元京都大学大学院理学研究科附属天文台長。1954年大阪府生まれ。2020年京都大学名誉教授。2021年一般財団法人花山宇宙文化財団理事長。2021-24年同志社大学特別客員教授。専門は太陽物理学、宇宙物理学、プラズマ物理学。理学博士。2020年ヘール賞受賞。磁気リコネクションが太陽における小スケールの突発現象(すなわちマイクロフレア、コロナジェット)から大スケールの爆発現象(すなわち太陽フレア、コロナ質量放出)に至る様々な現象で重要な役割を果たしていることを一貫して説明し、磁気流体・プラズマ物理学の理論的発展に大きな貢献をした(日本地球惑星科学連合ウェブ2021年度JpGUフェロー紹介サイトより)。主な著書に「太陽の脅威と人類の未来」(角川書店)など多数。