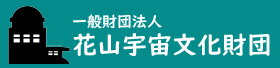京都大学花山天文台は1929年(昭和4年)に京都市山科区北花山で設立された、日本で2番目に古い大学天文台です。花山天文台は、清水寺の裏の東山にある京都大学の施設です。1929年の設立以来、火星観測や太陽観測で世界的な成果をあげてきました。「アマチュア天文学の聖地」とも呼ばれます。
京都大学花山天文台は、日本の天文学の歴史において非常に重要な役割を果たしてきただけでなく、花山天文台の建物や装置は歴史的・文化的な価値を持っています。その建物や望遠鏡などの装置は、当時の技術や建築の様式を伝える貴重な資料となっています。
花山天文台の施設は本館、別館、太陽館、子午線館(現在の歴史館)の4 棟が主要なもので、他に宿舎等がありました。主要4 棟のうち、太陽館は戦後に建て替えられ、他の3 棟が残っています。山科盆地から北西を望むと、東山に銀色のドームが2つ並び、多くの市民から親しまれています。
花山天文台の建築群は、抽象的な形態と合理主義的な建築観を追求するモダニズム建築という変革の時代の意匠をよく示す作例として貴重であると価値づけられます。2013年1月31日、花山天文台は、京都市の「京都を彩る建物や庭園」に“選定”されました。その後、調査と審査会を経て、特に価値が高いと認められ、2014年5月9日に「京都を彩る建物や庭園」に“認定”されました。2021年には、京都市京セラ美術館開館1周年記念展「モダン建築の京都」で紹介されました。
45cm屈折望遠鏡(本館)
この望遠鏡は昭和2年(1927年)、理学部宇宙物理学教室で購入したもので、昭和4年(1929年)に 花山天文台が創設されたときに移設されました。当初、口径30cmのレンズがついていましたが、昭和43年(1968年)に性能向上のため、カール・ツァイス製の45cmレンズに換装されました。これにより、 焦点距離が伸びることで鏡筒が長くなり、架台とのバランスが崩れるのを防ぐための工夫が施されています。それは対物レンズから入った光を末尾の反射鏡で受けて折り返し、鏡筒の中央付近に接眼レンズを設けるというものです。このため、一般的な屈折式の望遠鏡とは少し違った外観となっています。
また、日周追尾装置は購入当初からの重力時計を用いており、そのシンプルで精度の高い機構から現在でも活躍しています。
ザートリウス18cm屈折望遠鏡(別館)
この望遠鏡は、天文台が所有する望遠鏡の中で最も古い望遠鏡の一つです。1910年のハレー彗星接近の際に、ザートリウス社(ドイツ、ゲッチンゲン)より京都大学が購入し、その後、1986年同彗星の回帰時にも観測に使われました。現在、この望遠鏡には太陽を観測するためにリオフィルター、およびCCDカメラが取り付けられており、太陽望遠鏡として目覚しい研究成果を挙げています。現役で稼動している望遠鏡としては、日本最古の望遠鏡です。
また、口径11.5センチの屈折望遠鏡も同架されており、こちらは、白色光での黒点スケッチ用として活躍しています。
70cmシーロスタット望遠鏡(太陽館)
昭和36年に設立された太陽館では、シーロスタット望遠鏡としては国内最大の望遠鏡を用いて太陽の分光スペクトルを観測します。現在は、他の観測施設とともに大学院生の研究指導や理学部学生に対して課題研究と課題実習の実習教育を実施しています。
歴史館(旧・子午線館)
昭和4年に開館した子午線館は、天文台において、精密時計を補正するなどの目的のために用いられてきました。近年はその活躍の場を失い、歴史館として修復・保存されています。子午線館は大正から昭和の洋式木造建築として、日本の建築学史上において貴重な建築物となっています。歴史館は、3部屋に分かれており、西から天文台歴史室、天体・時計室、太陽スペクトル室として展示しています。
天文学や科学の魅力、歴史を感じることができる花山天文台にぜひお越しください。